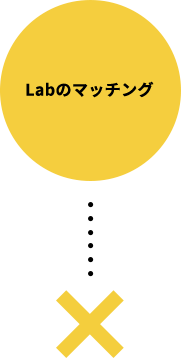-

-
ラヴィーレ川崎
廣川 秀人
上席ホーム長、介護福祉士
従来、ご利用者の排泄パターンの把握はマンパワーのみで実施しています。時間や工数がかかること、また知識・経験によるところも多く、ご利用者全員に実施ができていない状況がありました。
だからこそマンパワーによる排泄パターンの把握の確かさの確認や、より多くのご利用者の排泄パターンの把握が標準化・自動化・省力化できれば良いと考えていました。
Helppadを知った時、排泄介助の負担を軽減するテクノロジーだと思いつつ、果たして本当に排泄を検知しパターン化できるのか不安もありました。ただ、現場実証をする上でスタッフの負担が少なくてすむということが分かり、「それではやってみよう」と試してみることができました。


実際に使ってみると、マンパワーでの把握だけで確かかどうか不明だった排泄パターンが、Helppadでも同様の結果が出たため、これまでの把握も正しかったことが分かりました。スタッフたちのアセスメントが間違っていなかったという自信につながりました。また、今まで排泄パターンの把握を行っていなかったご利用者のパターンも把握できたことにより、介入回数や時間数の削減、空振りや汚染の削減につなげることができました。
現状のアセスメントは1時間おきにパット内を確認したり、記録をしなければなりません。それがHelppadを使用することにより、スタッフの負担の軽減はもちろんのこと、ご利用者のプライバシーへの配慮にもつながるのではないかと感じています。
現在はベッドの上にいる時間の長いご利用者が対象となっていますが、より幅の広い対象者に活用できるようになれば、現場としてより活用できるのではないかと期待しています。